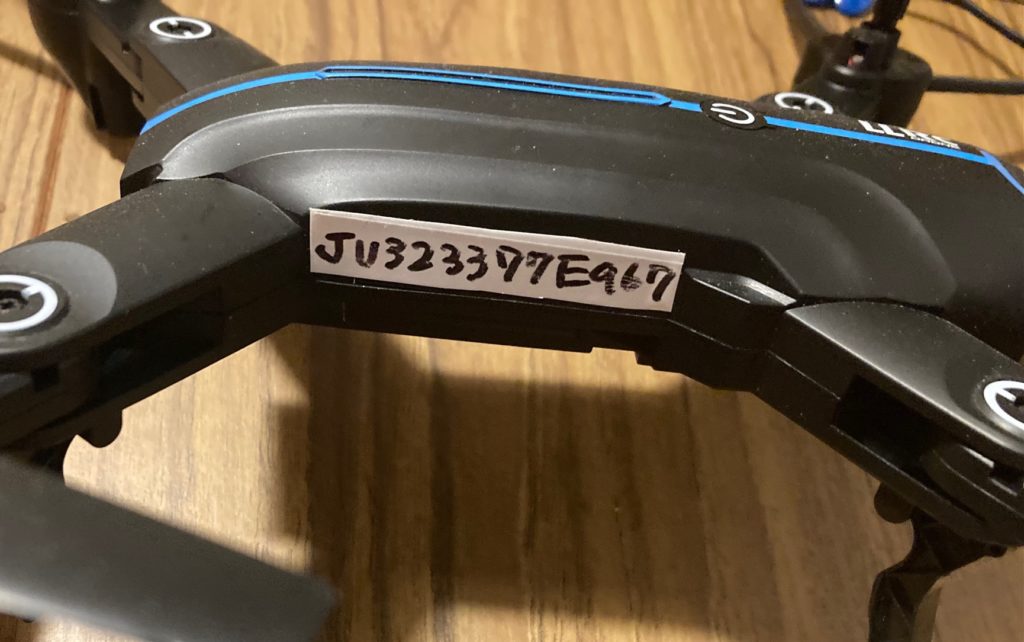奈良県王寺町で開業しています。
特定行政書士&申請取次行政書士&AFPの若林かずみです。
6月14日に入管難民法(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が参議院本会議で可決され、成立しました。
ニュースでもそれなりに大きく報道されていたかと思いますので、「何か改正されたらしい…」という程度にご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この改正法は、公布から3年以内に施行されることになっているため、2027年までには施行される見通しです。
改正法のポイントを以下にいくつかピックアップしてみました。
1)技能実習制度が廃止され、「育成就労」制度が創設される
技能実習制度は、発展途上国への技術移転を掲げていましたが、実態は、慢性的に人材不足に陥っている業界の労働力確保になっていることが問題視されていました。
そこで、30年続いた技能実習制度が、改正法によって廃止となり、「育成就労」の在留資格が創設されることとなりました。
「育成就労」の在留資格は、「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする在留資格です。
そして、この育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とします。
2)育成就労制度と特定技能の分野の対象を揃えることとなった
技能実習制度は、発展途上国への技術移転を目的とすることから、あくまでも帰国が前提となっていたため、技能実習制度と特定技能とでは対象職種がズレていました。
そのため、技能実習後に、日本に在留して働き続けられないケースがあったことから、新しい育成就労制度では特定技能と対象職種を揃えることによって、外国人労働者の長期就労を促すこととなりました。
3)外国人本人の意思による転籍も可能に
技能実習制度では、外国人本人の意思で職場を変更する(転籍)ことが原則として認められませんでした。転籍が認められないことにより、ハラスメントや低賃金労働の温床となっているのではないかと問題視されていました。
低賃金で劣悪な労働環境で働かされている技能実習生が失踪するなどのニュースを目にされたこともあるのではないでしょうか。
そこで、育成就労制度では、一定の条件付きで外国人本人の意思による転籍が認められることになりました。
改正法の詳細については、以下の出典先を参考にしていただければと思います。
《出典》
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要(令和6年3月15日閣議決定)(法務省)
改正法の概要(育成就労制度の創設等)
今後、人口減少により、確実に労働力が不足していくことから、益々、外国人労働者が増えていくことが見込まれます。
ただ、一方で、世界的に見て、日本が安い国になっている現在。
今後、このような状況が続けば、日本での労働を望む外国人がどれだけいるのか?
考えれば考えるほどに、前途多難であると言わざるを得ないところかと思います。
特定行政書士、申請取次行政書士(immigration lawyer)
AFP、法務博士(専門職)
若林かずみ(wakabayashi kazumi)
和(yawaragi)行政書士事務所
http://kazumi-wakabayashi-nara.com/
tel; <a href=”tel:0745277711″>0745-27-7711</a>
fax:0745-32-7869








.png)